金曜日, 3月 23, 2007
葛西の辺
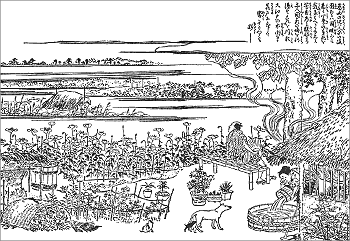 葛西の辺りは人家の後園あるは圃畔にもことごとく四季の草花を栽ゑ並みはへるがゆゑに、芳香つね馥郁たり。土人、開花のときを待ち得てこれを刈り取り、大江戸の市街なる花戸に出して鬻ぐこともっとも夥し 『江戸名所図会』
葛西の辺りは人家の後園あるは圃畔にもことごとく四季の草花を栽ゑ並みはへるがゆゑに、芳香つね馥郁たり。土人、開花のときを待ち得てこれを刈り取り、大江戸の市街なる花戸に出して鬻ぐこともっとも夥し 『江戸名所図会』『江戸名所図会』は江戸時代後期に斎藤月岑が先代の斎藤長秋(幸雄)と莞斎(幸孝)と書き継いだものを刊行した江戸の地誌。絵は長谷川雪旦による。
江戸時代も後期になると100万の人口を支えるために、江戸の西側の「武蔵野」、北側の「王子」、東側の「葛飾、足立」へと新田開発が進められた。その結果、江戸川区小松川では小松菜、練馬区練馬では練馬大根、文京区茗荷谷では茗荷、台東区谷中では谷中生姜が作られるようになった。『江戸名所図会』で書かれている「葛西の辺」は武蔵国葛飾郡葛西領、現在の江戸川区の葛西の情景を描いたもの。葛西の周辺では野菜ではなく、観賞用の草花が栽培されて出荷されていたという。ただ、ここでいう葛西というのは現在葛西と呼ばれてる地域よりもずっと広く、「江戸百景」に数えられる掘切の菖蒲園、つまり現在の葛飾区の辺りまでも指している。
木曜日, 3月 22, 2007
かねやす
 都営地下鉄大江戸線の本郷三丁目駅の近くにある「かねやす」。「かねやす」というのは兼康裕悦という口中医師つまり現在でいうところの歯科医が乳香散という歯磨き粉を売る店を構えたのがここ。
都営地下鉄大江戸線の本郷三丁目駅の近くにある「かねやす」。「かねやす」というのは兼康裕悦という口中医師つまり現在でいうところの歯科医が乳香散という歯磨き粉を売る店を構えたのがここ。「かねやす」は
『本郷も かねやす までは江戸のうち』
という川柳で知られた店だった。ちなみに、「かねやす」と平仮名なのは、別家の芝明神前の兼康との間で元祖争いが生じ、町奉行の裁定で本郷の兼康は平仮名で「かねやす」とすべきとしたことによる。
さて、「かねやす」が川柳に詠まれのは1730(享保15)年の大火の後。
大岡越前守忠相が防災上の理由から現在の本郷3丁目までの町屋を従来の茅葺から土蔵塗屋造、蛎殻葺にすることを命じた。その境目が「かねやす」で、「かねやす」は大きな店だったので目だった。
ちなみに、当時の「かねやす」の看板は赤穂浪士の堀部安兵衛が書いたと言われている。
水曜日, 3月 21, 2007
江戸城天守台
 かつての江戸の象徴の江戸城には長いこと天守閣は無かった。少し意外な気がしないでもないのは時代劇の影響だろう。
かつての江戸の象徴の江戸城には長いこと天守閣は無かった。少し意外な気がしないでもないのは時代劇の影響だろう。天守閣は家康、秀忠、家光の3代に渡って築かれ1636(寛永13)年に五層五階地下一階という容貌を人々の前に現した。しかし、1657(明暦3)年の振袖火事によって惜しくも焼失。今となっては想像を逞しくするしかないが、江戸城の天守閣は1606(慶長11)年に天守台部分を黒田長政、天守台の石垣を南部藩、津軽藩が、二層部分を伊達政宗が築いたという。それぞれの藩が総力を挙げたに違いない。だからこそ、現代に至ってもその名を留めている。形が無くなっても名が残るということは武士としては誉れ高きことと言えるだろう。
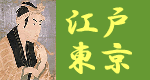
火曜日, 3月 20, 2007
馬を曳く埴輪
大阪府豊中市の大阪大構内にある5世紀末の待兼山5号墳で、馬を曳く人物形と、馬形の埴輪がセットで出土と大学が発表。馬曳人形は高さ64センチもあり、左手を上げて手綱を曳き、顔に入れ墨を線で表現しているという。一方、馬形は高さ78センチ、長さ98センチもあり、大型前方後円墳の出土物に比べても遜色ないもの。このようなセットの埴輪は最古と考えられるという。
