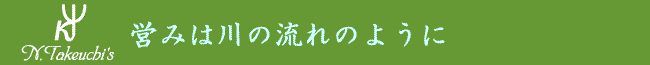江戸の原型
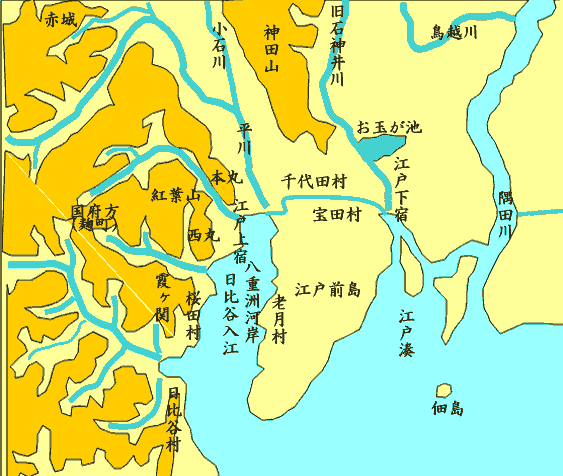
江戸という名は入り江の戸という意味から生じた言葉だと言われている。広い意味では現在の隅田川、荒川、中川、江戸川の4本の河口に広がる、武蔵野台地と下総台地との間に挟まれた約14キロの幅の東京下町低地と呼ばれる沖積地が江戸ということになる。しかし、歴史的な意味合いでの江戸は波蝕台地である駿河台を含む本郷台地の南に飛び出した江戸前島(大手町、丸の内、有楽町、内幸町、日本橋、宝町、銀座)が江戸とされる。江戸前島は西には日比谷入江(皇居外苑、日比谷公園、内幸町、西新橋、芝大門、浜松町)、東は石神井川が注ぎ込む江戸湊に挟まれ、丁度、「戸」のような形をしていた。
江戸の近くには入間川河口の浅草湊、中川(古利根川、古隅田川)河口の青戸、奥戸、渡良瀬川の松戸などがあった。しかし、これらの湊は江戸に比べて後背地が狭かったために江戸ほどには発達しなかった。
平安時代から鎌倉時代に掛けて、江戸の地を支配していたのは『吾妻鏡』に「坂東八ヵ国の大福長者」と記された江戸重長で知られる江戸氏だった。初戦に敗れた源 頼朝は一旦房総に逃れた後に、下総千葉氏、上総の上総氏の力を得て太白川(現江戸川)、利根川(現中川)を渡った。この時点で葛西御厨を所領としていた江戸氏の一族の葛西清重や豊島清元などの譜代の家臣が頼朝の陣営に加わり、江戸一帯を支配していた江戸重長にも参陣を命じた。
『吾妻鏡』の1180(治承4)年9月28日の条に、
御使を遣はして、江戸太郎重長を召さる。景親が催しによつて、石橋合戦を遂ぐること、その謂れありといへども、令旨を守りて相従ひたてまつるべし。重能・有重は折節在京す。武蔵国においては、当時汝すでに棟梁たり。専らたのみ思しめさるるの上は、便宜の勇士等を催し具して、余参すべきの由と云々
とある。秩父平氏の嫡流に当たる畠山重能・小山田有重兄弟が京都にいて不在だったために江戸重長を棟梁として参陣を命じたのだ。但し、江戸重長は葛西清重とは違って、この時点では平家方。そのために、1180(治承4)年10月4日の条では、
畠山次郎重忠、長井の渡に参会す。河越太郎重頼、江戸太郎重長また参上す。この輩、三浦介義明を討ちし者なり。しかるに義澄以下の子息門葉、多くもつて御供に候じ、武功を励む。重長等は源家を射たてまつるといへども、有勢の輩を抽賞せられずんば、こと成がたからんか。忠直を存ずる者は、更に憤りをのこすべからずの旨、兼ねて以て三浦一党に仰せ含めらる。彼ら異心無きの趣を申す。よって各々相互に合眼して列座する者なり
と陣に加わった後も警戒されている。